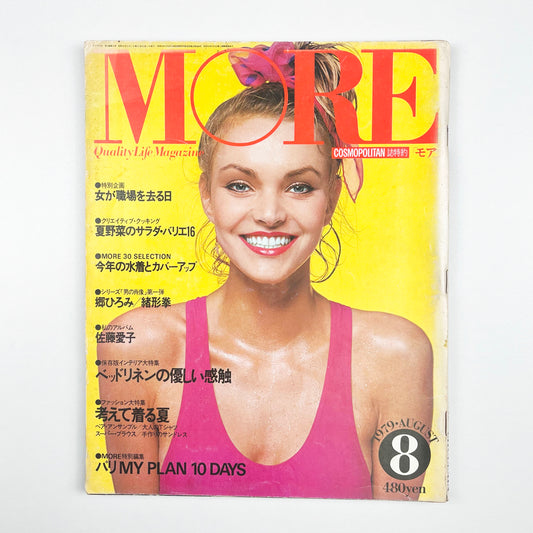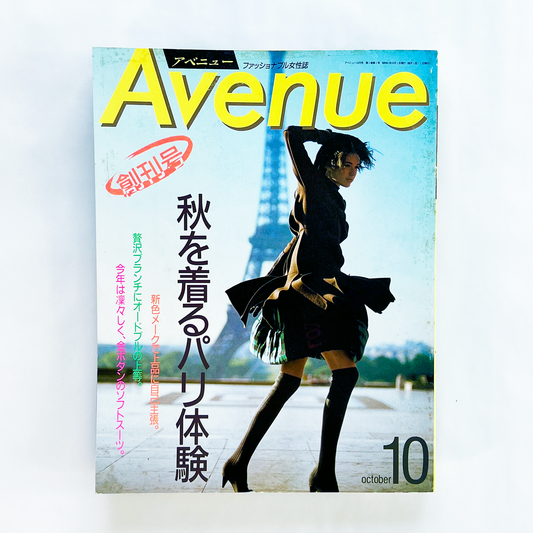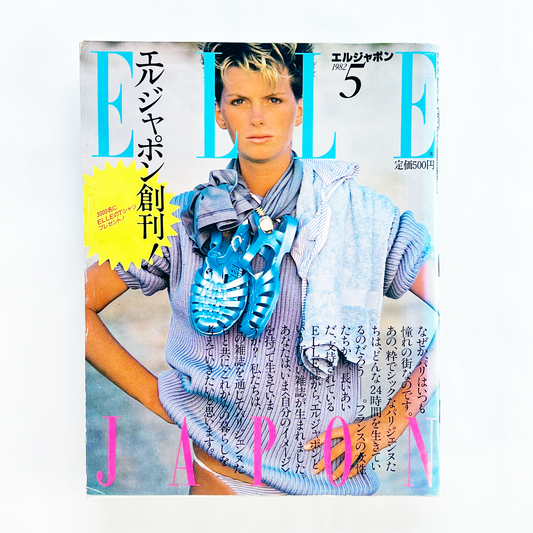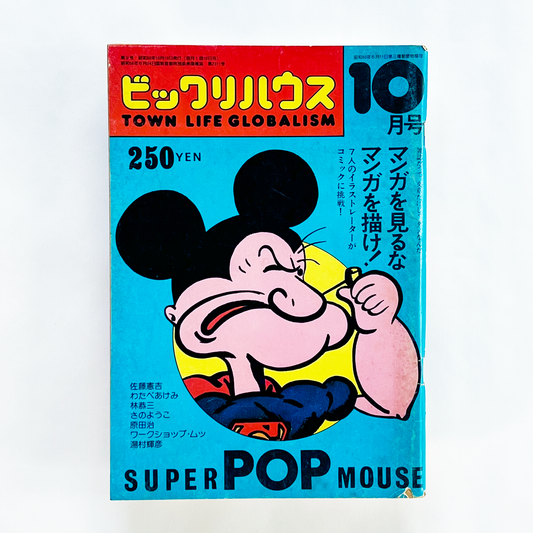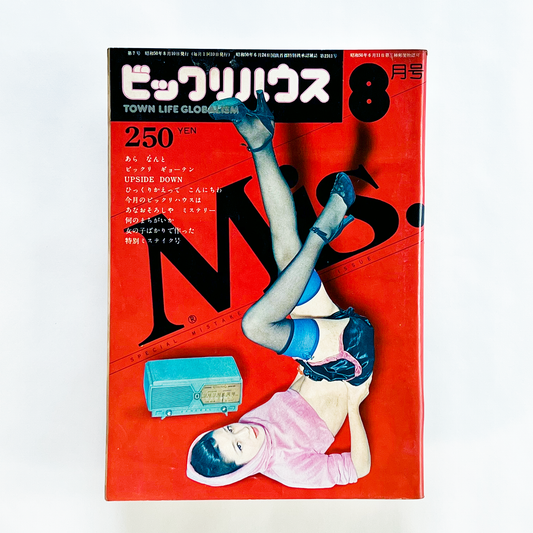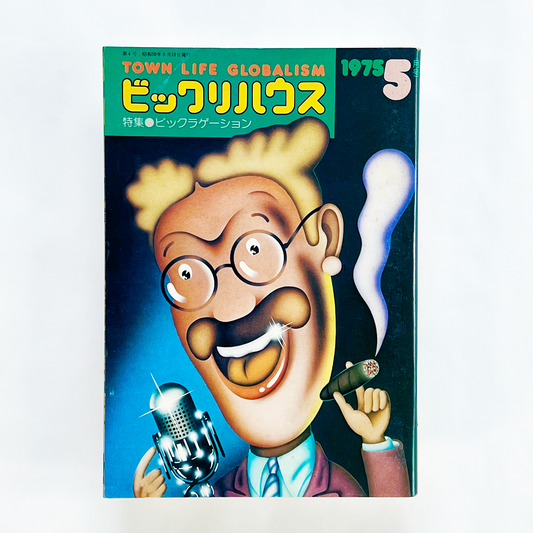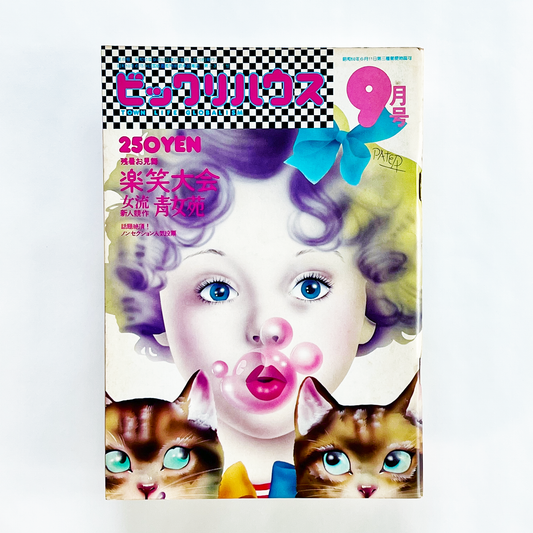-
 SOLD OUT
SOLD OUTMORE No.85 - 1984.7
通常価格 ¥1,100通常価格 -
 SOLD OUT
SOLD OUTMORE No.102 - 1985.12
通常価格 ¥1,100通常価格 -
 SOLD OUT
SOLD OUTMORE No.42 - 1980.12
通常価格 ¥1,100通常価格 -
 SOLD OUT
SOLD OUTMORE No.34 - 1980.4
通常価格 ¥1,100通常価格 -
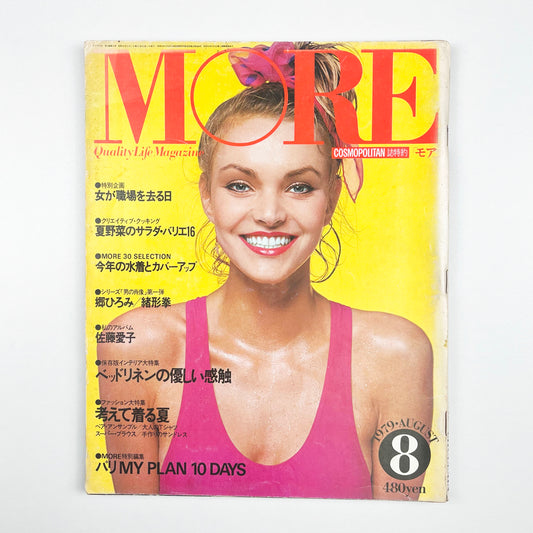 SOLD OUT
SOLD OUTMORE No.26 - 1979.8
通常価格 ¥1,100通常価格 -
 SOLD OUT
SOLD OUTMORE No.7 - 1977.1
通常価格 ¥1,100通常価格 -
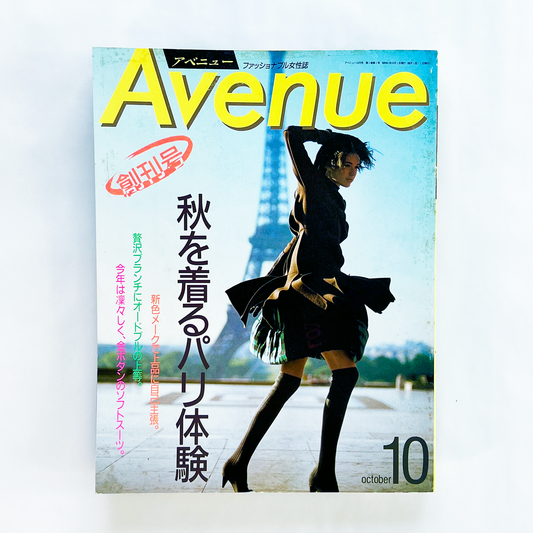 SOLD OUT
SOLD OUTAvenue No.1 - 1986.10
通常価格 ¥2,200通常価格 -
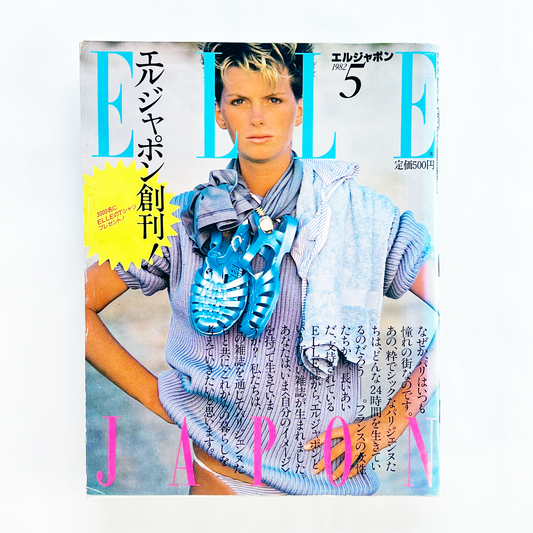 SOLD OUT
SOLD OUTELLEJAPON No.1 - 1982.5
通常価格 ¥2,750通常価格 -
ビックリハウス No.32 - 1977.9
通常価格 ¥2,200通常価格 -
ビックリハウス No.56 - 1979.9
通常価格 ¥1,650通常価格 -
ビックリハウス No.97 - 1983.2
通常価格 ¥1,650通常価格 -
ビックリハウス No.20 - 1976.9
通常価格 ¥1,650通常価格 -
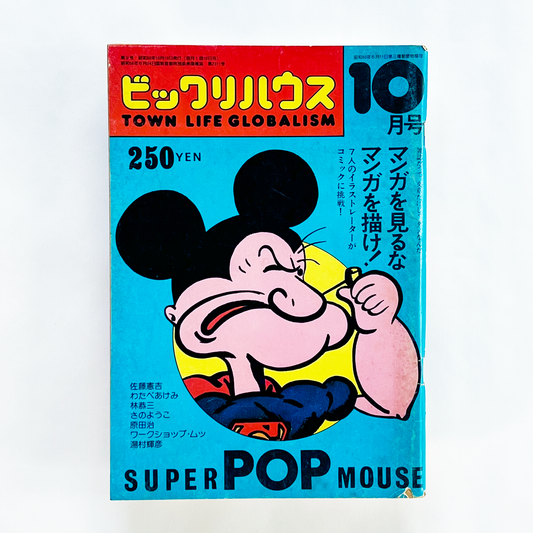 SOLD OUT
SOLD OUTビックリハウス No.9 - 1975.10
通常価格 ¥2,200通常価格 -
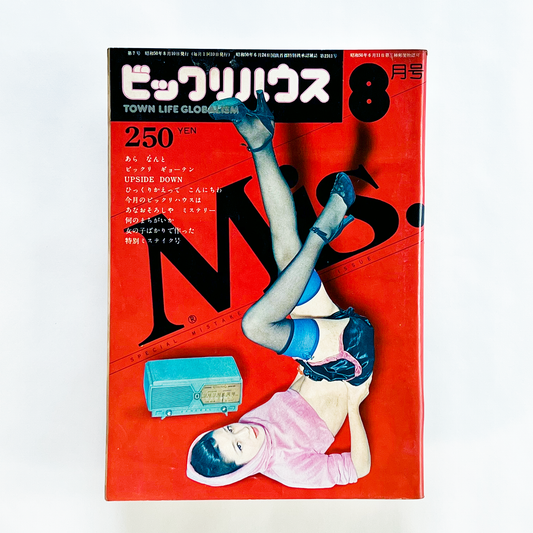 SOLD OUT
SOLD OUTビックリハウス No.7 - 1975.8
通常価格 ¥2,200通常価格 -
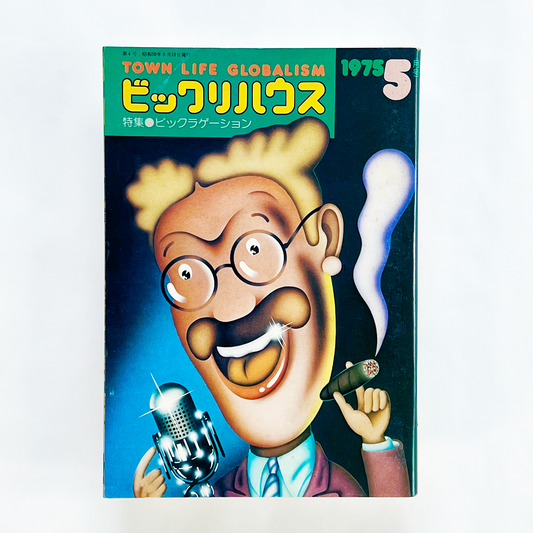 SOLD OUT
SOLD OUTビックリハウス No.4 - 1975.5
通常価格 ¥2,530通常価格 -
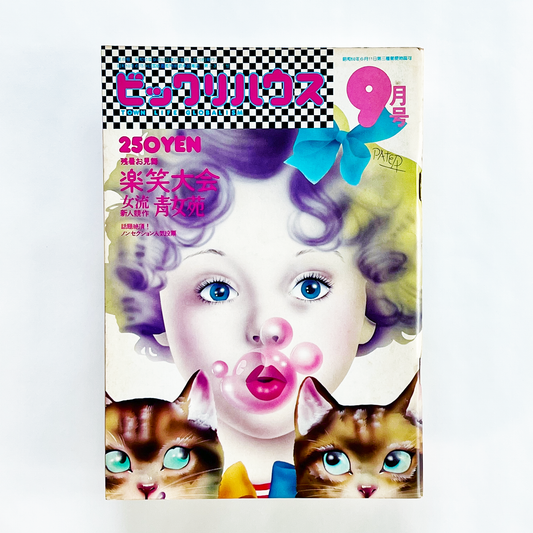 SOLD OUT
SOLD OUTビックリハウス No.8 - 1975.9
通常価格 ¥2,530通常価格